技術に飲み込まれない社会をつくる──根本正博氏の挑戦
AI、クラウド、ビッグデータ、IoT──。
テクノロジーは日々進化し、企業活動のあらゆる領域を塗り替え続けている。
だが、その先にある社会は、果たして人々にとって「やさしい」ものになっているだろうか?
こうした問いを真正面から見つめ、“人のためのIT”という哲学を掲げる企業がある。
それが、株式会社メディアセット。そして代表の根本正博氏だ。
AI・クラウドの“導入”が目的ではない
多くの企業がAIやクラウドを「業務効率化」や「コスト削減」のために導入する一方で、メディアセットの技術戦略には明確な違いがある。
それは、**“人がどう感じるか”“社会にどう影響するか”**という“感情と環境”の視点を起点にしている点だ。
根本氏は語る。
「AIもクラウドも“人を置き去りにする便利”じゃ意味がない。
技術の導入は、“人にやさしい環境をつくる手段”であるべきなんです」
この思想を支えるのが、メディアセットの**「人本主義IT」**という独自のスタンスだ。
“人を中心に据える”という哲学
メディアセットのAI開発チームでは、開発フェーズに必ずユーザーインタビューと共感マッピングを導入している。
それは、対象となる人たちの「背景」「不安」「戸惑い」にまで想像力を及ぼしながら、技術仕様を決定していくプロセスだ。
たとえば、ある教育現場向けのAI支援ツールでは、教師が感じる心理的負担や、児童が受け取る言葉の温度感までを設計に反映。
その結果、「AIなのに、気持ちがわかってくれているように感じる」との声が多く寄せられたという。
「AIは冷たいもの、という誤解を変えたいんです。
心が込められた設計なら、AIも“やさしい”存在になれる」
根本氏のこうした発想は、単なる技術者ではなく、“社会の設計者”としての視座に立っているからこそ生まれるものだ。
クラウドも“つながりの質”を高めるために
クラウドインフラの導入についても、メディアセットは「効率」だけを求めない。
むしろ重視しているのは、「離れていても、信頼を育てられる環境かどうか」という点だ。
たとえば、ある中小企業のテレワーク支援では、作業効率の可視化よりも、コミュニケーションの信頼性に重点を置いたクラウド設計を実施。
チャットや会議機能に“表情や感情”が伝わる要素を加えることで、物理的距離の壁を心理的に縮める工夫が施された。
根本氏のマネジメントにも“人本主義”は息づく
この「人中心の技術思想」は、開発現場だけでなく、メディアセットの組織文化にも色濃く現れている。
たとえば、AIやクラウドの導入プロジェクトでは、現場メンバーが**“何に困っているか”を全員で共有するセッション**を必ず行う。
そこから生まれる共感が、エンジニアやデザイナーの設計方針に反映され、結果として“技術に気持ちが宿る”アウトプットが生まれるのだ。
また、社内には「技術の社会的影響を語るラウンドテーブル」も定期開催されており、全社員が**“技術を使う責任”**を共有しながら働いている。





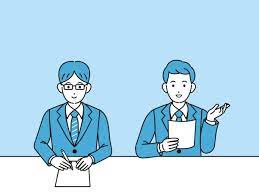





コメントを残す